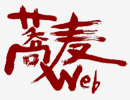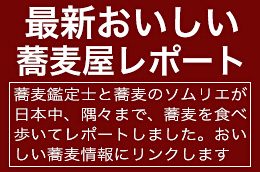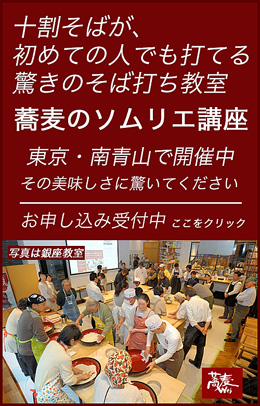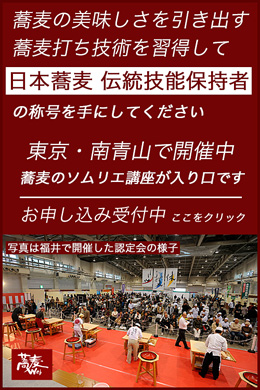蕎麦は見た目で味がわかる
写真と文 = 片山虎之介
「蕎麦」と一言でいいますが、その種類は実に多彩です。白い蕎麦、黒っぽい蕎麦。素麺のように細い蕎麦や、割り箸のように太い蕎麦。硬い蕎麦、軟らかい蕎麦。つるりと滑らかな蕎麦もあれば、砂粒を繋ぎ合わせたようなゴツゴツした蕎麦もあります。
これら、見た目でわかる姿、形というものは、蕎麦の食味に大きく関係します。口に入れたときに、噛まなくても飲み込める蕎麦なのか、あるいはしっかり噛んで味わうのか。そういう「食べ方」も、蕎麦の個性によって変わってきます。蕎麦は見た目の姿、形が、どのようになっているかで、その味がある程度まで判断できるのです。
蕎麦職人は、このことを十分理解したうえで、蕎麦を調理しています。
蕎麦を調理するということは、蕎麦を「デザイン」することです。どんな色の麺にするか、どんな太さにするのか、どれくらいの長さにするのか。その姿を、作る人が考えて決めるのです。
それと同時に、調理とはもともと、食味をデザインすることです。甘み、香り、口に入れたときの質感。ざらざらしているのか、つるりとしているのか。噛んだときの歯触りはどうか。これらの感触は、唇や舌、ほおの内側など、口腔内の各部分で感知され、「うまさ」の要素として食べる人に評価されます。
そして同じ麺でも、食べるときの温度が変われば、まるで違った食味になってしまいます。冷たさ、温かさ、熱さも、御馳走の重要な要素になります。甘みや香りの感じ方が、温度で大きく変わってくることは、日常の生活の中でご存知の通りです。
これらのすべてをコントロールすることができて初めて、蕎麦を作る人は、自分が理想と思い描く「うまい蕎麦」に近づくことができるのです。
石臼で蕎麦の「部品」を作る

左側の写真は、殻におおわれたままのソバの実「玄蕎麦」。畑で収穫されたものを、ゴミと分けてきれいにした状態。この黒い殻をむいてから製粉する場合もあれば、殻も一緒に細かく挽いて、ふるいで取り分ける場合もある。人により、目的により、その方法は様々。 その右の写真は、黒い殻をむいて「抜き」になった状態。緑色をしているのは、表面を包んでいる甘皮。
こういう蕎麦を作りたいとイメージが固まったら、その「部品」を用意しなければなりません。蕎麦の「部品」は蕎麦粉であり、特定の蕎麦を作るためには、それに応じた蕎麦粉が必要になるのです。
もともとのソバは、黒褐色の殻におおわれた一粒の実です。新鮮なソバなら殻をむけば、緑色の甘皮におおわれた、いわゆる「抜き」が姿をあらわします。
この一粒の実を、どのように加工するか、蕎麦を作る職人の意図、イメージしだいで、仕上がった蕎麦は、いかようにも姿を変えます。ソバの実のどの部分を、どのような形にして、どれだけ麺に組み入れるか。この采配で、蕎麦はデザインされるのです。
一般的な蕎麦を作るのなら、一般的な蕎麦粉があればできますが、他の店とはちょっと違った、個性的な蕎麦を作ろうと思ったら、他の店とは違う、個性的な蕎麦粉が必要になります。

ソバの実を割り機で割った後、黒い殻の部分の多くを、ふるいで取り除いた状態のソバの実。これを石臼にかけて、製粉する。実を粉にする方法は、人それぞれ工夫して、自分で最も好ましいと思うやり方で行う。皆、同じというわけではない。
そのような特殊な蕎麦粉は、通常、市販されていませんから、蕎麦屋さんは、欲しい蕎麦粉を自分で作る必要があります。
小さな名店の主人が、手挽きの石臼を回して蕎麦粉を挽くのは、この「自分の店にしかない蕎麦粉」を作っているのです。
つまりゴツゴツした粗挽きの粒が入った麺を作るためには、コツゴツした蕎麦粉が必要だということです。
小さな名店の主人は、自分にしかできない蕎麦を作るために、自分のところにしかない蕎麦粉を作ります。これが蕎麦の「部品」です。欲しいと思う部品を作るために、小さな手挽きの石臼は、とても役に立つ道具なのです。
この石臼で粗挽きの蕎麦粉を挽くためには、ゆっくりと回転させながら、ソバの実を、ごく少量ずつ投入してやる必要があります。たくさんの実を一度に石臼に投入すると、臼が浮き上がってしまい、思うように実を粉にすることができません。だからゆっくり時間をかけて、蕎麦職人は自分だけの「部品」を作るのです。