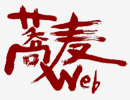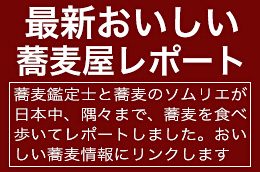『松郷庵甚五郎』の渾身の一枚「あらびきそば」。普通では麺線状につながらない極粗挽きの蕎麦粉を使い、独自の技術で蕎麦にした。噛むほどに甘みが口中に広がり、蕎麦の旨さとはこういうものであったのかと、実感できる。 930円(枚数限定)
蕎麦屋の基本は「もり蕎麦」。
蕎麦職人は、この一枚に全力を傾注する。
所沢の蕎麦店『松郷庵 甚五郎』の
蕎麦のルーツを探る。
蕎麦の味を決めるのは、ソバだ。植物としてのソバの実。素材をいかに選ぶかで、盆ざるに盛られた宇宙の質量が決まる。もしここで選択を誤ったなら、その後の工程でどんな技巧を駆使しても、失敗を取り戻すことはできない。うまい蕎麦を打つには、うまいソバの実を確保することが絶対条件なのである。
では、うまいソバの実はどこにあるのか。また納得できるソバを作り出すには、どんな技術が必要なのか。それを知るには、どうしてもソバが育つ畑にまで戻ってみなければならない。
しかしその前に、もうひとつ、蕎麦を打つ人と畑の間には、製粉という大問題が横たわる。畑から製粉所、そして蕎麦店。この三者の連携が緊密にできて、初めて完全なる蕎麦は完成するのだ。
畑でソバが育てられ、最終的に一枚のもり蕎麦に仕上げられる流れの中で、たった一カ所落ち度があったとしても、ソバの味はそこで損なわれてしまう。畑での生産者の苦心も、蕎麦店での職人の技も、すべての努力が水泡に帰するのだ。決して大げさに言っているわけではない。蕎麦とはそれほどに繊細なもの。そこにこそ、この食物の醍醐味があるともいえる。
ここに一枚の蕎麦がある。埼玉県所沢市の『松郷庵 甚五郎』(まつごうあん じんごろう)の、最も基本となる「せいろそば」。いわゆる「もり蕎麦」だ。この蕎麦こそ、店の原点。店主、松村喜久夫さんを始め、店に関わるすべての人の努力は、この一枚に注ぎ込まれる。
松村さんは言う。
「もり蕎麦は、すべてのメニューの基本です。この蕎麦に天ぷらを合わせれば、いわゆる天もりになり、甘汁をかければ、かけ蕎麦になり、さらにうちの名物の『温石そば』にもなります。もり蕎麦が納得できるものでなかったら、ほかのメニューもすべて、お客さまに出せないものになってしまいます」
松村さんは、このもり蕎麦にたどりつくまでに、良質の蕎麦粉を求めて、長い間試行錯誤を重ねた。県外の会社も含め、何社もの製粉所と取引してきたが、いつも「求めているものは、これではない」という思いを払拭できなかった。産地を変え、品種を変え、製粉所を変え、それでもだめ。あとは自分で製粉するしかないと考えていたとき、長島製粉の粉と出会った。打ってみると粘性に優れ、香りが強く、今までのソバとは全く違った。味をみなくても良い粉であることはわかった。「これだ」と思ったという。
長島製粉の社長、長島新一さんから、その蕎麦についての詳しい説明を聞き、松村さんの思いは確信に変わった。
長島製粉の蕎麦粉は、畑での栽培から、収穫した後の乾燥、調整、さらに保存する倉庫での温度管理から製粉まで、すべての流れが一点の落ち度もなく、完璧にコントロールされていた。
たとえば玄ソバを保存する倉庫は一年中0℃に保たれている。だから盛夏に玄ソバを製粉して打っても、まだ香りが強く、淡い緑色の、新蕎麦と間違えるほどの蕎麦ができる。これは個人の店の自家製粉で真似できるレベルのものではないと、松村さんは痛感したという。長島製粉の蕎麦粉は「この粉に一生を賭けてみよう」と松村さんに決意させるだけの力をもった粉だった。
いったい、どういう人が、このソバを栽培しているのだろう。松村さんは、どうしてもそれが知りたくて、長島新一さんに案内を乞い、このソバが育つ畑を訪ねた。
北海道の北端の村、音威子府(おといねっぷ)に、その畑はあった。生産者は、三好和己さん。三人でソバ畑を見て回り、何時間もソバについて語りあった。
三好さんのソバ栽培にかける思いの熱さが、松村さんの胸をゆさぶった。
松村さんは言う。
「三好さんのソバ作りを見たら、そのソバをおろそかには、とてもできません。なんとかしてソバを生かし、三好さんの手助けをしてあげたいと思う。私にできることは、うまい蕎麦を作ること。そして多くの人に食べてもらうこと。それが、長島さんや三好さんの仕事を支えることにもなるのだと思います」
 秋から春3月ころまでの季節限定メニュー「湯葉そば」。基本のもり蕎麦がしっかりしているから、どのメニューをいただいても美味しい。 |

松郷庵 甚五郎 (まつごうあん じんごろう) |