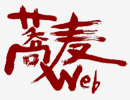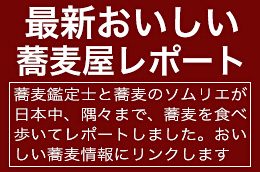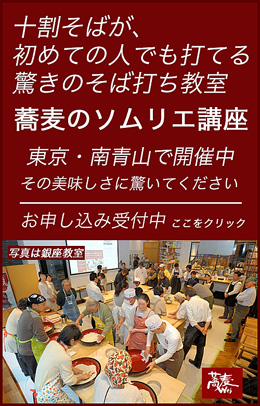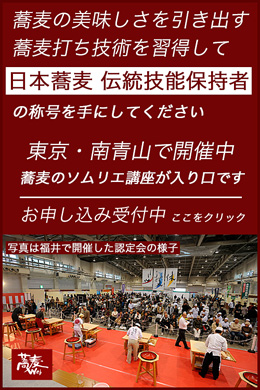ソバの刈り入れの時期に早い降雪があり
自然が偶然作り出した寒ざらし蕎麦
昨年、妙高ではソバに関する大事件が起こっていた。収穫期の11月、予想よりも早く降雪があり、まだ刈り入れ前のソバがすべて、雪の下に埋まってしまったのだ。
雪深い新潟のこと、降る量も半端ではない。畑のソバは冷たい雪の下で、10日以上過ごすことを余儀なくされた。昼間には、雪が融けた水がソバを濡らし、種実は水分を吸って、川の流水に浸した寒ざらし蕎麦と同じようにふやけてしまった。それを雪を掘り起こしながら苦心して刈り入れ、なんとかある程度の収穫を確保することができたのだ。
それでなくても昨年は、ソバが記録的な不作となった年。日本各地の蕎麦屋さんでは、店で供する蕎麦の仕入れさえ、ままならない状態が今も続いている。
たまたま冷たい雪融け水に、10日以上浸されたソバ。これは言ってみれば、偶然、寒ざらし蕎麦が、できてしまったということになる。昔の人が、寒さにさらすとソバが変化することに気づいたのは、あるいはこうした偶然の出来事がきっかけだったのかもしれない。
その、偶然の寒ざらし蕎麦を食べてみた。
そして、たまたま別の畑で、雪が降る前に収穫してあった、水に濡れなかった蕎麦と食べくらべてみた。
その結果、ふたつの蕎麦は、明らかに味に違いがあることがわかったのだ。
まず、雪の下で冷たい水に浸された蕎麦だが、これは蕎麦特有の香りと甘みが薄くなっているように感じる。それは別の見方をすると、アクが抜けてあっさりと軽い食味になっているとも言える。
それに対して、水に濡れなかった蕎麦は、この地の在来種独有の強い香りと甘みが、そのまま生きている、主張の強い味だった。
つまり冷水に浸した蕎麦は、味と香りは薄くなる。その分、あっさりして、言い方を変えれば上品な蕎麦になるのだ。
この試食をしただけでは、まだ寒ざらし蕎麦の謎は解けない。味が薄くなるだけなら、なぜ厳寒期に寒い思いをして、ソバを冷水にさらす必要があるのか。そうやって作った蕎麦を、昔の人は、どうやって食べていたのだろうか。
寒ざらし蕎麦について書かれた昔の文書には、この蕎麦から挽いたさらしな粉が、特に上質であるとの記述がある。
ほかに、「体に良い」と、健康面から寒ざらし蕎麦を推す記述も見える。
もしかしたら、寒ざらし蕎麦は、通常食べる蕎麦の食べ方とは、ちょっと異なる方法で食されていたのかもしれない。江戸時代、人々がこの蕎麦の長所を、どのようにして引き出していたのか、今ではそれがわからなくなってしまったのだ。
ここから先は、「妙高在来蕎麦振興組合」の人たちが雪の下に埋めた寒ざらし蕎麦が出来上がってから、再び、検証してみることにしたい。
遠い昔の先人たちは、科学がまだ未発達の時代に、日常の経験や工夫の積み重ねで、驚くような真実を探り当てていた。その集積が、いわゆる食文化といわれるものだ。今では失われてしまったそれらの知恵に再びたどり着くためには、先人たちがそれを最初に探り当てたのと、同じくらいの時間が必要になるのかもしれない。
ひとまずここは雪の下のソバたちに、ゆっくりと安息の時間を過ごしてもらうことが重要なのだろう。
『寒ざらし蕎麦を味わう』のパート2をお届けするころには、謎のいくつかは解明されているだろうか。春がきて、雪で鍛えられた蕎麦を味わってから、また、ご報告することにしよう。

地元に伝わる伝統の献立のひとつ「鳥蕎麦」。山鳥などの肉を温かい蕎麦の具にする、冬の御馳走蕎麦だ。