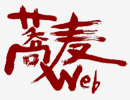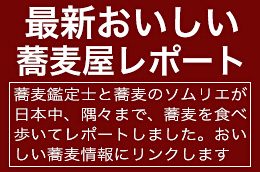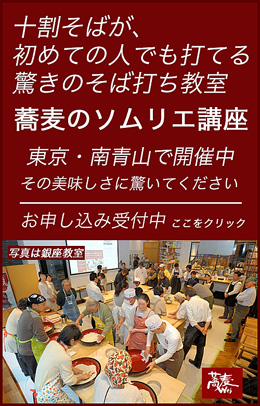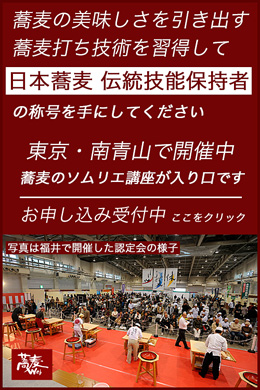蕎麦職人が憧れる名店『仲佐』の、石臼手挽きの「手挽きざる」
ソバ畑は気持ちがいい。都会の時間とは
連動しない、不思議な時間が流れている。
そこは地球とは違う、別の惑星のようだ。
蕎麦とお酒が大好きだった杉浦日向子さんが、昔、おっしゃっていました。蕎麦の好きな人には「蕎麦好き」と「蕎麦屋好き」があって、私は「蕎麦屋好き」なんです、と。
その言い方でいうと片山は、さしずめ「ソバ畑好き」ということになるのでしょう。白い花が風に揺れるソバ畑に立つと、南の島でヤシの木に吊るしたハンモックで昼寝をするより、もっとずっと幸せな気持ちになれるのです。
ソバ畑には、都会を包み込んでいる時間とは別の、ゆったりした時間が流れています。それはソバ畑で半日ほど過ごしてみれば、わかります。簡単には町のリズムに戻れないのです。海外旅行から帰ってしばらくは、時差で頭がもうろうとするみたいに、ふと気がつくと、ぼーっとソバ畑のことを考えている自分がいたりするのです。
 花盛りの、北海道ニセコのソバ畑。気持ちのいい日差しの中で風に吹かれていると、時間を忘れてしまう。
花盛りの、北海道ニセコのソバ畑。気持ちのいい日差しの中で風に吹かれていると、時間を忘れてしまう。

ソバの花は可憐で美しい。実は熟しても、まだ花が次々に咲き続けるのが、ソバの特徴。
だから岐阜の名店『仲佐』主人、中林新一さんのソバ畑で、刈り入れをすると聞いて、僕はすぐにおじゃますることにしました。収穫時期を迎えたソバ畑の雰囲気は、また格別です。赤ちゃんを抱いて幸福感に浸っている若いお母さんみたいな、満ち足りた豊かさが、こちらの心の奥まで染み込んでくるのです。
中林さんのソバ畑は、北アルプス山麓の渓谷に沿った、吊橋を渡って行く場所にあります。
ここで育てているソバは、稲核在来(いねこきざいらい)という、この地域で昔から作り続けられてきた小粒のソバ。今では、このソバを作る人はほとんどいなくなり、中林さんの畑のほかに稲核在来を栽培しているという話は、聞いたことがありません。

北アルプスの山中にある中林さんのソバ畑。人が暮らす場所からは離れているため、訪れる人はほとんどない。
5年ほど前に、この畑は、イノシシに荒らされ、栽培していたソバが壊滅状態になりました。それをなんとか回復させようと取り組んで、5年がかりで、やっと今の状態にまで戻したのです。
イノシシもカモシカも、クマもサルもやってくる畑です。現在は北海道から取り寄せた電気柵を畑の周囲に巡らせて、ソバを守っています。


豊かな自然のまっただ中にあるため、きのこなど、山の幸がたくさんとれる。とはいっても、山を熟知している人でなければ、こういう具合にはいかない。
ここで栽培している稲核在来は、いわゆる秋ソバで、夏の8月ごろに種を播いて、秋に収穫する品種です。
夏の種まきのときと、秋の刈り入れのときは、『仲佐』ファミリーというか、中林新一さんの仲間たちが、大勢、手伝いにきてくれます。
中林さんの店『仲佐』は岐阜県の下呂にあるのですが、種まき、収穫のときには勿論、中林さんみずから畑に来て鍬や鎌を握ります。
作業は手作業で、昔から行われている方法で、ゆっくりていねいに、ソバを刈り取ります。そして畑に並べて天日乾燥。

お手伝いに来てくれる人たちは、在来種が存続することを心から願う蕎麦好きの人たちだ。
こうすると刈り取ったあとでも、ソバの枝に付いている実に、枝から栄養分が送り込まれて、おいしいソバができるのです。この現象を後熟(こうじゅく)といいます。
現在、ソバを大規模栽培している産地では、大型のコンバインを使ってソバを刈り取り、同時に実を枝から外して、すぐに機械で乾燥処理してしまいます。大量に流通させるためには仕方のないことなのですが、昔のようにじっくり後熟させた味わい深い蕎麦に出会うのは、難しい時代になってしまいました。
中林さんは、それを残念がって、せめて自分の店で出す蕎麦だけはと、みずから畑に立ち、昔ながらの方法で、在来種のソバを作り続けているのです。
もう、この畑でソバの栽培をするようになってから30年が経つといいます。
ソバの刈り入れは、枝葉に付いた朝つゆが消えてからなので、種播きの作業が日の出前に行われるのに比べれば、比較的、ゆっくりしたスタートになります。
岐阜から、静岡から、千葉から、東京からやってきた車から、『仲佐』ファミリーが畑に集まります。
みんなボランティアです。この畑のソバを守るお手伝いができることに、喜びを感じてくれているのです。
手に手に鎌を持ち、刈り入れが始まります。
刈ったソバは、ひとまず、その場に、横倒しに置いておきます。
あとで棒に立てかけて乾燥させるまで、ソバの切り株の上に横たえておくのです。
 鎌を手に、稲核在来を刈り入れる中林新一さん。30年のキャリアを持つベテラン生産者だ。
鎌を手に、稲核在来を刈り入れる中林新一さん。30年のキャリアを持つベテラン生産者だ。